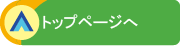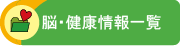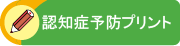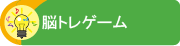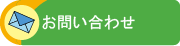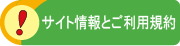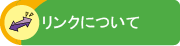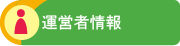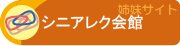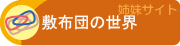脳を老けさせる10のNG習慣とは
「脳の学校」代表取締役の医師、加藤俊徳氏によると、日々の習慣が脳の成長をさまたげ、脳を老けさせているそうです。
ここでは、加藤氏による脳を老けさせる10の習慣をご紹介します。あなたはいくつあてはまっていますか?
日経ウーマンオンライン(日経ヘルス) に掲載されていた記事を基書きました。
サイト管理者の考えや知識も追加されているため、記事をまとめたものとは異なります。
脳老け習慣1:21時以降に食事
21時以降は体とともに脳もお休みモードに入るのだそうです。この時間に食事を取ると、脳も活動させられてしまい、ゆっくり休めないのだとか。
会社から帰るともうこの時間は過ぎているという方も多いと思いますが、なるべく軽めにするなどの対策は取れそうです。
脳老け習慣2:人の悪口を言う
否定的な言葉は脳を鈍化させるそうです。ネガティブな言葉を口にした時、一番よく聞こえてしまうのが自分の耳なので、非常に脳に悪いのだとか。
否定的な言葉は脳に多大なストレスを与えます。投げかけた相手の脳にもストレスを与え、なにもいいことはありません。たまの愚痴は仕方ありませんが、日々愚痴ばかり言っている人は自分の脳にストレスと与え、また聞いてくれている人の脳にもダメージがあることを考えて、なるべく早く気持ちをきりかえることが出来るように心がけると良いですね。
脳老け習慣3:会社と家の往復のみ
毎日決まり切ったマンネリな生活は脳が慣れることで脳の働きは鈍化するとのことです。たまには通勤ルートを変えてみては。
このサイトでも何度か取り上げた「日々のマンネリ」です。脳はとにかく「ナマケモノ」です。慣れてしまったら頑張ろうなんて考えないんです。日々の中に脳にとって新鮮なものを取り入れていかないと脳の働きはどんどん鈍くなってしまいます。
脳老け習慣4:太りすぎる!
肥満などの生活習慣病は脳細胞を傷つけるそうです。
脳細胞を傷つけるとは怖いですね。肥満は万病のもとと言われますが、脳細胞さえ傷つけるという強敵のようです。肥満の解消はなかなか難しいことですが、習慣1の「21時以降に食事をとる」ことを控えたり、習慣8の「イライラする」をポジティブな考えで乗り切るようにすることで、ついでに痩せることを狙ってみては。まぁしかし、「痩せなくちゃ」自体がストレスになるのですけれど。
脳老け習慣5:運動不足!
習慣4に引き続き、万病のもと系です。加藤氏によると、体を動かさないと、夜の睡眠の質が下がるそうです。すると体も脳も休まらず、疲労してしまうわけですね。また、運動は脳に刺激を与えますから、その意味でも運動は必要です。
運動はダイエットにもプラスですし、ウォーキング等の有酸素運動は脳に非常に良い刺激を与えます。
脳老け習慣6:10cm以上の高さのハイヒールを履く
高すぎるヒールが足、腰、肩等に負担をかけ、コリを生み、それによって痛みが出ます。痛みは脳の「思考系」の領域で、痛みが継続して起こることで判断力や思考力が低下するそうです。
ハイヒールだけでなく「痛み」全てがいけないということですね。コリは継続的な痛みを生みますから、なるべく体に負担を掛けない装いや行動が必要と言うことですね。
脳老け習慣7:焦る・慌てる・急ぐ
ゆっくりと物事を考えて行動すると、神経細胞の枝が伸び、脳の各領域がうまく連動してくれるそうです。
急いだり慌てて素早い行動をすると脳はキビキビ動いている気がしてしまったりしますが、逆なのですね。よく考えることで脳の神経細胞の枝がのびるというのは覚えておきたいですね。脳細胞の数が減っても、この神経細胞の枝があちこちと上手くつながって連動することで脳はさらに成長するのですから。
脳老け習慣8:イライラする
イライラにも種類がありますが、ここでいうイライラは、「脳の同じ部分を酷使したことによるイライラ」だそうです。すると、脳の血流が悪くなり、怒りっぽくなるそうです。
つまり、職業病みたいなものかもしれません。職業柄、脳の同じ部分ばかり使う方はきっととても多いでしょう。特に事務職やエンジニア等、パソコンに向かって、人と余り会話をすることもなく日々過ごしている人はかなりイライラがたまっているはず。休日は脳の全く違う部分を使うことでリフレッシュを。
脳老け習慣9:ケータイ・スマホを手放せない
加藤氏によるケータイ・スマホを手放せないとは、これによって覚える能力が劣化するということのようです。つまり、電話番号も覚えずにすみますし、毎日の予定も書きこんでおけば覚えなくていい。少しはアナログに行動してみてはとのことです。
学生であれば覚えることって日常茶飯事ですが、社会人になるとなかなか覚えなくてはならないものも無くなってきます。そうなると、意識しない限り「覚える」というスキルを使わなくなってしまうということです。意識して「覚える」スキルを使うと脳が活性化します。目標があったほうがいいならば、資格試験勉強とか新しい技術を身につけてみるとか、何か始めてみてもいいかもしれませんね。
脳老け習慣10:人の目を気にしすぎる
人の目を気にするとなかなか楽しめません。脳は快楽が栄養になりますから、この快楽が人の目を気にしすぎることで得られず、結果的に脳が成長しないそうです。
脳はナマケモノですが楽しいことが大好きです。心地よいと感じることで成長するのですから、脳に良いことをしてあげましょう。感動は脳の快楽ですから、感動できる映画をみるとか、大自然を見に行くとか、晴れた日に散歩を楽しんでみるとか。脳に良い刺激を与えることで脳は喜んでくれます。
[ トップページ ]
認知症予防知識情報一覧
認知症予防知識情報一覧ページへ
▼以下、一部抜粋
老化と脳トレーニング
ひらめくことで脳の老化はストップする
認知症予防に効果があるのは唯一パズル等である~トロント大学~
ワーキングメモリ(作業記憶)トレーニング
テレビゲームで50歳脳が若返る?(アメリカ)
同じテレビを見るのでも脳に差が出る
人への悪口は自分の脳にダメージを与える
イライラしない心がけが大事
アメリカ・アルツハイマー病協会提唱「脳を守る10カ条」
脳を守る10カ条を軽~く、ずぼらに考えてみた
本当の『老化』は75歳から始まる
アルツハイマー型認知症の大半は7つの危険因子で予防できる
認知症が気になったらデュアルタスクを鍛える
認知症のリスクを確実に下げる食事とは
認知症を知る
認知症の前段階、前認知症の症状とは
認知症の早期発見の大切さと難しさ
認知症患者は全国推定患者数462万人 2013年度調査
認知症患者数は2050年には世界で1億人超
長谷川式簡易知能評価スケール ~認知症かどうかのテスト~
認知症施策推進5か年計画オレンジプラン(厚生労働省)とは
認知症対応に大切な『否定しない』こと
認知症についてまとめました。
新しい情報や対処法など様々な情報を随時更新していきます。
脳血管性認知症についてまとめました。
突然の発症が怖い病気。予備知識としてぜひご覧下さい。
転倒による骨折から長期入院や寝たきりとなり、認知症になる方が多数います。ポイントは・・・。
糖尿病はそれ単体で認知症になる危険性があります。
正しい知識で糖尿病を防ぎましょう。
どんなに節約していても、怖いのが突然の病気等による出費です。
シニアの為の保険についてご紹介します。
レクリエーションプリントで脳活性化
シニアレク会館(姉妹サイト)に、無料で使えるパズルプリントが多くあります。
ボケ防止クイズ&ゲームで認知症予防
辞書ゲーム 思い出しゲーム ブロック途中経過推理ゲーム 漢字ばらばらゲーム 瞬間記憶脳刺激ゲーム 違うところ探しクイズ ダジャレを考えようゲーム
百人一首を書く 一覧
計算問題(足し算問題)他の問題へのリンクも